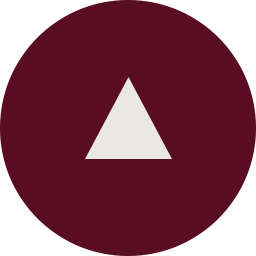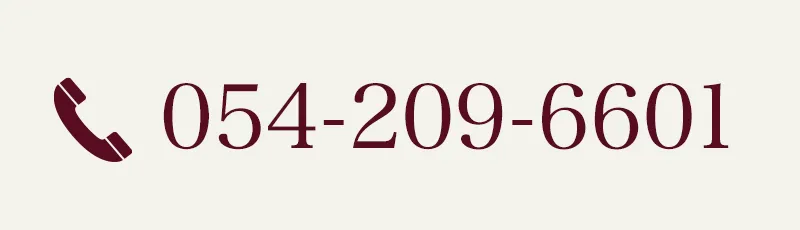無痛分娩
当院では硬膜外麻酔を用いた無痛分娩を希望者に行っています。
この麻酔方法は、硬膜外腔(脊髄の存在するクモ膜下腔よりも外側の空間)にカテーテルという細いチューブを留置し、身体の外に出したカテーテルを通して、持続的に局所麻酔剤を注入する麻酔方法です。無痛分娩で最も一般的な麻酔方法で、⿇酔で痛みは緩和されますが意識はあります。⾚ちゃんが⽣まれてくる瞬間もしっかりとご体験いただけます。痛みが少ないので、体⼒の消耗も少ないのが特徴的です。
「無痛分娩」と「和痛分娩」の違いはなんですか?
麻酔方法に違いはありません。産婦様からしたら、陣痛による痛みが無ければ無いほど魅力的だと思いますが、痛みを完全に取り除いてしまいますと、後述するような無痛分娩のデメリットが生じやすくなります。痛みの程度をコントロールし、許容の範囲内に抑えることが、無痛分娩のメリットを最も享受しやすくなる最大のコツです。
メリット
- 麻酔薬により陣痛が和らぐため、リラックスしてお産に臨めます。結果母体の体力消耗が少なくなります。
- 麻酔が産道にも効き緊張が解けるため、子宮口が広がりやすくなります。このため、お産で一番時間がかかる、子宮口が全部開くまでの時間が短縮しやすくなります。
デメリット
- 麻酔薬が効き過ぎると陣痛が弱くなり、分娩進行が遅くなることがあります。
- 陣痛が弱くなると、回旋異常(お母さんの骨盤の中での赤ちゃんのまわり方が悪くなる)が増えます。
- 子宮口が全部開き、赤ちゃんの頭が下降すると、産婦様は自然に「いきみ」が出現し、赤ちゃんを押し出そうとします。麻酔が効き過ぎると、この「いきみ」が無くなります。結果、分娩の進行が止まってしまうことがあります。
「当院では、経産婦様を対象に計画分娩で無痛分娩を行っています」
無痛分娩では、希ではありますが生命に直結する重篤な合併症が起こりえます。これまで関わってきた無痛分娩(前職の順天堂大学医学部附属順天堂医院、当院)において、そのような合併症の発生はありませんが、希な合併症であっても一定の頻度でどの施設においても起こりえるため、大切なことは合併症が重篤に至る前の早期発見と、その対応が可能な環境の中で無痛分娩を実施することです。
そのための安全性の確保には、医師や助産師、看護師らの十分なマンパワーが欠かせません。この観点から、当院では曜日を選んで、診療時間内に計画的に無痛分娩を行っています。経産婦様の多くは、お産が順調に進行しやすいため、(自然の陣痛を待たない)計画分娩のスケジュールが組みやすい特徴がありますが、初産婦様の場合には、お産がなかなか進まず、数日かかることが多いです。長時間の麻酔薬の曝露は、お腹の中のお子様にも出生直後に一時的ではありますが影響が及ぶことがあるため、当院では経産婦様を対象に計画分娩で無痛分娩を行っています。
初産婦様の場合には、このような計画分娩ではなく、自然に陣痛が来た後に無痛分娩を併用していく「オンデマンド型の無痛分娩」の方が、分娩進行への影響が少なく済みますが、24時間体制でこれを行える医療施設はかなり限られます。初産婦様の無痛分娩希望者には、ご期待に沿えませんが、お産の現場では安全が最優先ですので、ご理解のほどお願い申し上げます。
無痛分娩は事前の予約制とし、分娩制限を行っています。経産婦様で無痛分娩を希望なさる場合には、妊婦健診通院中にお早めに医師まで希望をお伝えください。
妊娠36週以降は、毎週の健診で内診を行い、子宮口の状態(お産への向い具合)を確認します。十分な熟化(お産が近い子宮口の状態)と、お腹の中のお子様の成長の具合を考慮し入院日(経産婦様の多くは38週台)を決定します。入院後は、硬膜外カテーテルを留置し、事前に十分な麻酔効果を確認した上で、翌日に陣痛促進剤を用いた分娩誘発を行います。痛みが辛くないよう、適宜麻酔薬を調整してきますが、腰と肛門の痛みと、押されるような感じは残ることがあります。
合併症とその対応について
無痛分娩による重大な合併症は、麻酔薬の少量分割投与と厳格なモニターによる観察により、早期に対応して重症化を防ぐことに努めています。
無痛分娩の比較的軽度の合併症
- 微弱陣痛
麻酔薬を使うことで陣痛が弱くなります。多くの場合、子宮収縮剤による陣痛促進が必要となります。 - 硬膜穿破による頭痛と神経傷害
頭痛や足の痺れなどがしばらく残ることがあります。頭痛は一旦生じますと、約1週間程、足の痺れはほとんどのケースが一過性であり、2~3ヶ月で症状が消失します。
無痛分娩の重大な合併症(発生頻度は希ですが、重大な影響が生じることがあります)
- 麻酔薬のくも膜下腔への迷入
硬膜外腔は粗な組織であり、麻酔薬は投与量に応じて一定の領域にしか留まりません。しかしくも膜下腔は、髄液で満たされているため、投与した麻酔薬が髄液に混じると麻酔薬が広がりやすく、脊髄全体に麻酔が及ぶことで、血圧低下や呼吸停止につながる場合があります。早期発見し呼吸を補助することによって、呼吸停止による低酸素脳症を防ぐことができます。 - 麻酔薬の血管内迷入
硬膜外腔は血管が豊富です。妊婦の場合、さらに血管が怒張しています。カテーテル挿入時に、偶発的に血管を破り、カテーテルが血管内に迷入することがあります。この状態で麻酔薬を多量に投与すると、局所麻酔薬中毒を起こし、重症のケースではけいれん、不整脈・心停止を引き起こす場合があります。このような症状が起こる前に院内に常備してある脂肪製剤点滴により麻酔薬の血中濃度を低下させ、重症化を予防することができます。 - アナフィラキシーショック
重症のアレルギーで呼吸困難、血圧低下を引き起こす場合があります。救急カートに常備してあるアドレナリンを使用することで対応が可能です。
このように命にかかわるような合併症もあります。これらは、どんな達人が行ってもある一定の確率で起こるため、早期に発見し重症化を防ぐことが大切です。麻酔薬を多量に一度に投与せず、少量ずつ、時間を空けて、分割投与すること、厳格なモニターリング(合併症を早期に発見するための観察)、「口の違和感」「耳鳴り」「息苦しい」「両下肢が動かない」などと言った自覚症状の早期発見で、重症化を防ぐことが可能です。何か変わった自覚症状があれば積極的にお知らせください。なお、麻酔薬投与時は、麻酔薬の効果の確認、バイタルサイン(血圧、心拍数、酸素飽和度)の確認、自覚症状の確認、下肢の運動機能の確認を頻回に繰り返して行います。
無痛分娩の費用
- 無痛分娩加算10万円 (硬膜外カテーテル持続注入薬剤の追加が生じた場合には2000円/1本)
- 計画分娩加算1.5万円/1日 (分娩促進剤の追加が生じた場合には3000円/1本)
*当院の無痛分娩では、ほとんどのケースが誘発分娩初日で出産に至るため、上記合計が12万円を超えることはほとんどございません。
「無痛分娩に関する方針と分娩件数」(2023年1月時点)当院はJALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)認定施設です.
【医師】
| 産婦人科 | 常勤医師数 : 2人 |
|---|---|
| 非常勤医師数 : 4人 | |
| 麻酔科(帝王切開に対応) | 非常勤医師:3名 |
| 小児科 | 非常勤医師:1名 |
【分娩件数】
| 分娩数 | 無痛分娩件数 | 予定帝王切開件数 | 緊急帝王切開件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 254 | 4(1.5%) | 18 | 16(6.7%) |
| 2018 | 304 | 4(1.3%) | 28 | 23(8.3%) |
| 2019 | 338 | 2(0.5%) | 42 | 14(4.7%) |
| 2020 | 419 | 2(0.4%) | 36 | 15(3.9%) |
| 2021 | 413 | 2(0.4%) | 25 | 17(4.3%) |
| 2022 | 369 | 9(2.4%) | 29 | 17(5.0%) |
- 妊産婦さんの本人希望による無痛分娩受け入れ/あり
- 無痛分娩導入対象/経産婦を対象にし、計画無痛分娩に対応
- 麻酔方法/硬膜外麻酔※
※硬膜外麻酔とは:無痛分娩の際に、背中に入れたチューブから麻酔薬を入れ、陣痛の痛みを軽減する麻酔の方法。
【無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況】
- 麻酔器/あり
- 除細動器/あり(AED)
- 母体用生体モニター/あり
(心電計、非観血的自動血圧計、パルスオキシメーターなど) - 蘇生用設備・機器/あり
(酸素ボンベ・流速計、マスク&バッグ、喉頭鏡、気管チューブ(6、7)、吸引装置・カテーテル - 緊急対応用薬剤/あり
(アドレナリン、硫酸アトロピン、フェニレフリン、静注用キシロカイン、ジアゼパム、チオペンタール、プロポフォール、硫酸マグネシウム、静注用脂 肪乳剤、代用血漿剤、乳酸化リンゲル液、生理食塩水など)
【急変時の体制】
- 母体救急蘇生
産婦人科医常勤医師1名および助産師2名、看護師3名がJCIMELS受講済 - 新生児救急蘇生
産婦人科医常勤医師1名および助産師 7名、看護師4名NCPR受講済 - 重症症例搬送
静岡市当番医輪番制により当番病院へ搬送を考慮するが、緊急時は最寄りの県立総合病院への搬送を優先する。 方法/救急車
【無痛分娩麻酔管理者】
- 依藤 崇志
- 産婦人科専門医
- 麻酔科研修歴および実施歴
賛育会病院:2003年10月~2004年9月(帝王切開自家麻酔で対応。同期間で約25件の脊椎麻酔、硬膜外麻酔を対応)順天堂大学医学部附属順天堂医院2006年1月~3月(脊椎麻酔18件、硬膜外麻酔39件、静脈麻酔7件、ラリンジアルマスクによる全身麻酔22件、気管挿管による全身麻酔76件を対応) - 無痛分娩実施歴
2006年~2014年 順天堂大学附属順天堂医院:116件
2015年~ 依藤産婦人科医院: 24件 - 講習会受講歴
無痛分娩の安全な診療のための講習会 カテゴリーA/B受講済み
ALSO、J-MELS受講済み
無痛分娩マニュアル(PDF:1MB)
無痛分娩看護マニュアル(PDF:212KB)
無痛分娩説明書(PDF:540KB)